「朝ごはん食べなさい!お昼まで体がもたないよ!」
母親からこんな風に叱責されつつ、寝ぼけ眼でジャムをたっぷり塗ったトーストを無理くり口に頬張り、バタバタと身支度を整えて学校に向かうという経験、誰しもしたことがあるのではないか?
そして、「体がもたない」と言われていたはずだが、逆に朝食を摂った体は重く、頭は冴えず、眠気と闘いながら昼を迎えたことも少なくないはず。
そして昼食を迎える。食後、かなりの高確率で眠気に襲われて、午後の授業中に船を漕いだ人もかなりいるのではないか。
食事によってエネルギーに満ちて、体はバリバリと動けるようになるはずだったのでは?
なぜこれほどまでに体はだるく、頭は鈍くなるのか?
食事が体のエネルギー源となること、必要な栄養素を摂り入れる手段であることは間違いない。
しかし、大事なことを忘れていないだろうか?
私たちの体は車ではない。そして、食事はガソリンではないのだ。
つまり、摂り入れたものがすぐにエネルギーになるのではなく、エネルギーとするためには「消化」と「吸収」という大事なプロセスを経ることを忘れている人が多い。
一般的に、胃による消化に3時間程度、腸による吸収に3〜5時間程度かかると言われている。
食事の後は胃と腸が一生懸命働いてくれていることを意識できている人が少ない。
1日3食食べたとすると、胃はどれほど働いているか?
7時に食べたご飯は10時ごろまでかけてやっと消化される。そして少しの休憩を経て12時にまた食事に対応する。15時ごろに少し長めの休憩を迎え、19時ごろにその日最後の消化に取り掛かり、22時に本日の業務終了。まあ、働けなくはないスケジュールだが、ちょっとブラック企業の香りがする。
では、3食食べた際の腸はどうだろう?どれほど働かされている?
7時に取った食事が胃によって消化されたものは10時以降順次腸に送り込まれてくる。こちらも早く見積もって3時間かかるため、13時ごろまでは仕事をすることになる。2時間休憩を挟んだのち、12時に食べた昼ごはんの消化されたものが15時に送り込まれてくる。それを18時ごろまで吸収していき、4時間休憩後の22時に最後の仕事に取り掛かる。終わるのは翌1時だ。
総労働時間は胃と一緒だが、睡眠中は消化吸収の業務効率が落ちる。電気を落とされた事務所で、デスクライトだけで仕事させられているような状況だからだろう。結果として、1時を超えて働き続けてくれていることが常態化している。
遅くまで本当にお疲れ様、俺の腸。ブラック企業で働いてくれていて本当にありがとう。
このように内臓が働いてくれていることを意識できていない人があまりにも多すぎる。
実は胃での消化は食べたものによって時間が異なる。炭水化物なら2〜3時間、タンパク質なら3〜4時間、脂質が多いとさらに時間がかかるようだ。よって、何を食べたかによっては胃と腸の労働時間が変わってくる。また、先に述べたリズムには間食や夜食は含まれていなかった。それも含めると、体は常に消化か吸収のために動いていることになる。
自分の体にこんな過重労働を強いていることを意識してみると、たくさんの顕在化した症状の数々が思いつくはずだ。胃もたれや胸焼けは、消化にかかる負荷が高すぎて起きている。便秘や軟便も、消化しきれないと腸が悲鳴をあげている証拠。こうした疲弊した腸の状態は、お肌の質を著しく低下させる。乾燥肌、にきびなどの吹き出物は腸が毒素を排出しきれなかったものの影響だ。髪の毛も例外ではない。腸が正しく栄養を吸収できないことで、パサつき、抜け毛、白髪の増加などといった形で影響を及ぼす。
不健康そうな人は、一見してその雰囲気で読み取れる気がしないだろうか?それは、上記したような顕在化した症状が体のここかしこに出ているからだ。そして、より深刻な影響を与えるのは実はメンタルだ。メンタルを安定させるために非常に重要なセロトニンは、実はその9割が腸に由来する。腸が正しく機能しないとセロトニンが生成されづらくなり、結果、イライラや不安、集中力の低下、やる気のなさなど心の状態を低下させていく。
このように、食事はエネルギー源となるものだが、そのエネルギーを適切に摂り入れるには胃と腸の働きをしっかり考慮に入れる必要がある。
にも関わらず大抵の人が胃と腸に1日最低でも9時間労働を強いている。しかもそれはいわゆる「定時」の話で、大抵の人が残業を強いている。不規則なリズムで食事を摂ることや、間食をとることなどによってだ。結果、12時間越えの労働が当たり前になり、胃と腸は疲弊しまくっていく。週休二日制で週末に休めるならまだ救いようがあるが、ご存じのように私たちのほとんどは365日勤務をモットーとしている。絶望的な労働環境。なぜこれを皆許容しているのだろうか?
3食食べないと体がもたない、という謎の信仰心を持っているからだろう。
日本に3食文化が根差し始めたのは江戸時代後期からと言われている。つまり、この文化はまだ200年足らずのものなのだ。しかも、明治以降はどんどん文明が栄えていき、人の暮らしは楽ができるようになってきている。体を動かさないでもいろんな物事を成し遂げられる便利なもの〜乗り物、家事をサポートする器具類、昭和に入ると電化製品も台頭〜がどんどん出てきて、エネルギーを無駄遣いしなくて良い生活になっているのにも関わらず、エネルギー源としての食事はかつての不便で無駄に体を動かさなくてはいけない時代よりたくさんとるようになっている。これによりどんな社会が生まれた?
肥満や成人病の蔓延だ。日本の成人の25%程度が糖尿病かその予備軍であると言われている。科学が発展し、医療技術も飛躍的に向上しているにも関わらず、万病の元である糖尿病のリスクをこれほど多くの人が抱えているのは、間違いなく「食事」に関するイメージが狂っているからだ。
このイメージを変えていこう。
いつも僕らの体の中で昼夜問わず働いてくれている胃と腸。彼らの働きがあって、健全な消化と吸収が成り立つ。健康になりたいなら、ブラック企業から脱する努力をすることだ。まずはこのマインドセットからスタートしたい。
そして、常識を疑おう。
世間が言っていることの全てを信じるのではなく、何が正しいかについて自分でとことん調べる心構えを持ちたい。テレビの情報はそれぞれのテレビ局の思惑、CMスポンサーの願いに沿って脚色・調整されている可能性があることを頭の片隅に入れておきたい。その観点で考えると、新聞すら情報として全てを字面通りに受け入れるのは危険ということになる。詳しくは後日「情報断食」の回に語りたい。
テレビやSNSで発信されるジャンクな情報から身を守り、書籍や論文などのような健全な情報を読み下していく。専門書を何冊も読み、求めている分野の「真理」を探す気構えでいたい。僕はそんな意識で食の分野の文献を3〜40冊は読んだ。結果、1日3食を肯定的に書いている本は皆無に等しかった。あるとすれば、成長著しい若年期と、大人の場合はボディビルダーやスポーツ選手などの「一般的ではない活動」をしている人の体についてのみ、1日3食必要の論理が当てはまるのみといっていい。
つまり、一般的な大人、99.9%の大人は、3食は間違いなく食べ過ぎなのである。
まともな企業は1日8時間勤務、そして週休二日制であることが一般だ。
これを体でやってみるのはどうだろう?
16時間断食と、OMADの組み合わせが、このリズムを作り出す。
1日8時間しか食事を取らないのが16時間断食。
これは昼ごはん(12時)と晩御飯(19〜20時)のみを食べる1日2食にすると簡単に実現できる。
寝ている時間も断食にカウントできるので、だいぶストレス度は低い。
おそらくほとんどの人が、2〜3週間で体に馴染ませることができる。
そして、ほどなくして胃が軽くなり、胸焼けがなくなるだろう。
そして腸がしっかりと機能するようになり、便秘は解消し、肌荒れも軽減していく。
OMADはどうだろう?
これは「One Meal A Day」の略語で、1日1食を表す。
完全週休二日、つまり完全な断食を入れるのはかなりハードルが高い。
食事はメンタルにも影響を与えると言ったが、適切な食事は喜びにもつながる。
特に家族や友人との食事は幸せな時間であるのは間違いない。それも無くしてしまうのはかえって不健康になりえる。
であれば、誰かと一緒に食事する可能性が一番高い時間のものだけ摂り入れることにし、あとは食べないことにする。
私の場合はそれが晩ご飯になる。妻と1日起きたことを話したり、一緒にドラマや映画を見て楽しむ憩いの時間になっている。
これがOMADだ。これを週に1〜2日いれるだけで良い。
このOMADをすると、16時間断食の時を上回る集中力の向上と、アンチエイジング効果を実感できる。
特に肌のツルツル感がやばい。空腹を、自分のすべすべの肌を優しく撫でることで紛らわせるほどだ。感性が研ぎ澄まされ、創作意欲が湧いてくる。読書量が増し、インプット量が増えた脳は、まとまった考えをアウトプットしたがる。結果として僕はブログなどにそれを転化し、自分のマインドセットを強化したりアップグレードしたりすることに成功している。
断食の効果は体に及ぼすものだけにとどまらない。時間とお金が節約できるのだ。
少し長くなってきたので、これは明日語ることにしよう。
今日の記事だけでも断食することが異常なことではなく、本来の人間の営みに戻る行為であるとさえ感じられるようになってきたのではないか?
明日とその翌日の語ることを聞けば、それはやったほうがいいことではなく、やるべきことだという意識の変化を経験するだろう。
ではまた明日。

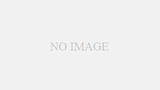
コメント